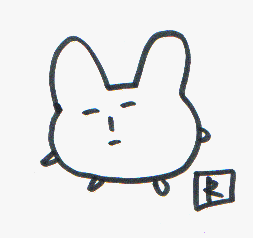●龍河洞●
http://www.ryugadou.or.jp/

鮭の石。
せっかく高知まで出てくるんだ、遍路巡礼だけじゃなく、普通の観光もゼヒしてみよう、ということで始まりましたこの企画。今回は龍河洞でした。
勇者が小さい頃に一度来たことがあり、面白いところだったので江口もどうか、というお誘いでありました。まあ、鍾乳洞なんか見たことないしな、面白そうだからいいんじゃないか、ということになりました。軽く下調べ。公式サイトから、いくつか情報を得ようとするが、見学休業日が書いていなかった。
月曜休業ってことはないですかー?
大丈夫でした。でも月曜日が休業じゃない、ってことだけで、年中無休であるとの確認は取っていない。年末年始のスケジュールとかどうなんだ。まあ、それはまた次に行くときにでも考える。
えっとね、場所はね、さっきの大日寺から、更に県道22号線を北へ。途中から道が『龍河洞公園線』と名前を変えるので、それに乗る。
ああそうか、このあたりは『龍河洞』で喰ってんだな、なんでもかんでも『龍河洞』なんだな、と思っていたら勇者に「それを言ったら観音寺は何でもかんでも『銭形』だ」とツッコまれた。はい、まったくその通りでござんす。あとは『デンデケ』とか。
一本道だし、わかりやすいところなので迷わず到着。
そこは見事な観光地でした。
言っていいですか。
江口、こんなベタな観光地が大好きです!
駐車場に大きな土産物屋と食べ物屋、龍河洞入り口に向かって軽い傾斜の道になっている、そこの両脇にずっと土産物屋。ちょっとでも前を通りがかると「よってらっしゃいみてらっしゃい」。龍河洞まんじゅうやら龍馬せんべいやら刃物やら尾長鶏やら、ともかく高知県名物をこれでもかと陳列。
大好き。こんな空気大好き。
用意された長い参道(注※江口の身近で同じシチュエーションといえば金比羅さんなので、ついこう呼ぶ)の両脇を冷やかしながら進む。
入り口付近には食堂も。名物料理もいろいろ有るそうです。
そこで見つけた、『いのししラーメン』『いのししカレー』の文字。どうやらこの当たりでは、この山の幸が名物であるそうな。勇者とふたり、「わざわざここで食べなくても、今、うちの冷凍庫にあるから」などと感想をいいつつ進む。
と、江口達の前にいた男女4人組のうちのお姉ちゃんが看板を見て。
「いのししだってー。気持悪ーい」って。
オイシイヨ! イノシシ、オイシイヨ! 豚肉みたいな甘やかされた味じゃない、大人の味がするよ! と彼女の背中に訴えつつ、我らも洞窟入り口を目指します。
龍河洞は山を一つ登る形であります。
入り口はまず、階段を上る。真横にエスカレーターもあったけど、健康な我らは歩く。
そして頂上の切符売り場で入場券を買い(大人¥1000)、洞窟内撮影可の確認もし、いよいよ中に入ります。
はしゃぐ江口。
すごーい。すごいぞ、自然の神秘。なんだこれは。こんなのが長い年月をかけて出来上がるのか!
純粋に、面白い。調子に乗って中の写真をとりまくる。後続の数グループに追い抜かれながら満喫する。
こんなにゆっくり進んでいるのは江口達だけかもしれない。でも面白いんだもんな、本当に。
中はひんやりと涼しい(16度だった)。至る所に水が流れているから。
道は狭く、ところどころで頭をぶつけそうな所もある。下は濡れているので、油断していると転ぶ。
そして所々の見所で、ガイドのおばちゃん達がいる。おばちゃんはまるでテープレコーダーのように流暢に案内をしてくれる。見た目は普通なのに、黙っていれば一般観光客と変わらない格好なのに、プロの技を見た気分だ。そしてガイドを真剣に聞いているのも江口達だけ。えーっと、皆さん、あんまり興味ないですか? それとも江口、はしゃぎすぎ?
見所はいろいろあり、そして要所要所にナイスな命名が施されている。『龍宮殿』やら『シャンデリア』やら『玉簾の滝』やら。まあ風雅。
で、最初は調子に乗って写真をがんがん撮っていたのだが、だんだん追っつかなくなって諦めた。
しまいにはこんなのを撮ったり。

お客様休憩用。
一人しか座れません。しかし、所々にある。親切だ。
そうして歩くうちに、こんな場所も見つけました。

<!>WARNING
冒険コース入洞について
安全確保のため(不明)ナビゲーターが(不明)
あなた方のサポートの為同行します
冒険コース!!
実は事前下調べの際、このコースの事も知って、行ってみたいと思ってはいた。今回は到着時間が未定だったため予約が出来ず諦めていたのだが、こういうのを見せられると行きたくなるってのが人間じゃないでしょうか。
ちなみに詳細はというと、ヘルメットにヘッドライトを付けて、時には這いながら進むような場所らしい。なので事前注意事項にも、「汚れても構わない服装で」とある。
そしてこの金網の向こうに見える、その危険空間。
行きたーい。
見たーい。
這いずり回りたーい。
いつか行ってやる。いつか行ってやるぞ冒険コース。
出口近くには弥生時代の遺跡なぞも残っている。『神の壺』と名付けられたそれは、当時の壺が鍾乳石で覆われたもの。
うわあ、歴史のロマンだー。
「壺の化石です」と解説されて、眼から鱗が取れたような気分。ああ、こういうものも現代まで残るんだなあ。すごいなあ、地球ってすごいなあ。なんかさっきから、陳腐な表現しかできない自分が悔しいなあ。
全行程は30分ほど歩きます(たぶんわしらはそれ以上かかっているはずだが)。
遺跡まで見終えると、ようやく出口。
しかしそこは山頂でした。
これからずっと、新緑を堪能しながら山をくだります。
途中で「近道」と交わる分岐点がありますが、我々はそのまままっすぐ行きました。
両脇に土産物屋が。
オウ。
さてさて、洞窟を堪能したので、次は博物館のほうへ移りましょう。
2階建ての建物で、1階では龍河洞の歴史を紹介するビデオなどが流れ、その他いろいろ歴史を勉強するためのパネルやら模型やらが並ぶ。あとは近所の観光地紹介とか。
資料が並ぶのはいいが、ここは管理されているのだろうか。
ブロントザウルスの模型とかあったしな。イベントのポスターが2005年だったりしたしな。
と、油断していたが。2階にあがるとこれはまた。
立派な資料館がそこにはありました。
詳細は割愛するが、発掘品や収集品が丁寧に保管され、それらが分かりやすく陳列されていました。ついつい長居する我々。いつものことだが。
ついでに、壁に貼られていた、この資料館の年表を見てみる。
昭和56年に、公開50周年として、こうやって資料の再編成とかがなされたらしい。そしてこの頃に、勇者(当時7歳)はここへ来たようだ。
そしてその頃から、ここの展示品は変わっていないのだろう。生き証人が言うんだ、きっとそうだ。
資料館を出ると、銅像を見つけました。

山内浩先生の銅像です。
そもそも鍾乳洞、いまでこそ遊覧コースが整備されているが、そんなものが無かった時代には足を踏み入れることなど敵わない秘境であったことでしょう。
それを探検し、全容を解明したのがこの先生。すごい人だ。
そんなにすごい人なのに、作業服とヘルメット姿で銅像。こういう銅像もアリか。
では次ー。珍鳥センターです。
この県には天然記念物の尾長鶏がいます。だから、それの資料館も用意されて当然でしょう。
もちろん入ります。
鶏小屋だった。
アタリマエっちゃ当たり前なのだが、そこは鶏小屋だった。
鳥の前でフラッシュを焚くのがはばかられて撮影をしなかったので現場写真がありません、ここは公式サイトの写真を見て頂きたい。
通常、こういうサイトに載せる写真は、一番いいアングルで、ステキに見えるようにされていることだろう。
しかし、サイトの写真を見ても、言い訳の聞かないほどに鶏小屋。
尾長鶏なんか、尾っぽを伸ばすためだと言われて箱に押し込められていた。そんな人生歩みたくないだろうに。
とりあえず資料館なのだからと、全部の鳥の顔を拝む。
えーと、うずらチャボは丸っこくて可愛いです。七面鳥はひときわでかくて憎たらしいです。たいていの鳥はつがいで一小屋だったのに、軍鶏だけは1羽で入れられてました。軍鶏なんだな。
と、全部の鳥を見て気が付いた。
毛並みが綺麗。
そう、さっきから鶏小屋鶏小屋と罵ってみたが、よくよく見ると鳥そのものは綺麗なのだ。白い羽の鳥をみるとよく分かる。真っ白。きちんと管理がされているのだろう、侮って申し訳ない。
そんなふうに珍鳥を堪能する我々だが、後から来たおばちゃんグループたちにどんどん追い抜かれていく。
我々はこんな場所までじっくり見てしまう人種なのだな、と再認識させられました。
珍鳥センターの1階は土産物屋です、もちろんな!
降りるとベンチがあって、茶を勧められました(っても、おみやげ試飲)。梅茶でした。ごめん、江口、梅キライ。
で、ベタな土産物屋が大好きな江口は、そのままそこの土産物を物色する。
と。

鰹のタタキストラップ発見ーーーーーー。
うわああーーー可愛いーーーーーめっちゃ欲しいーーーーーー。
欲しいといいながら、ここに写真がある。
はい、買っちゃいましたよ、衝動買いですよ。ちなみに買ったのは『タタキ2個付き』(\650)。2個付きって! このほかにも『タタキ大皿盛り』『皿鉢料理』(\800)もあった。どれにしようか最後まで悩んで悩んで選んだ2個付き。現在は江口の携帯電話に付いています。職場のみんなに自慢もしました。思い残すことはありません。
その他にも、坂本龍馬皮財布にもココロ奪われた江口がいる。
ベタ大好き。
全ての施設、それぞれを満喫し、帰りは最初の参道沿いの土産物屋で、鰹珍味(ハラミ\500)と芋けんぴ(\300)を買う。珍味は売店の人に「これはお酒のつまみによく合うんですよ」とさんざん勧められた。後に判明することだが、高知人のその発言に嘘はなかった。
降りてきたところにある食堂で、ちょっと遅い昼ご飯にする。
中のテーブルで店員が普通にご飯食べてた。そうか。
以上で寄り道は終わります。
それでは元の、遍路道に戻りましょう。
(※ここの文章を書いている今日は7月7日。いろいろスマヌ)